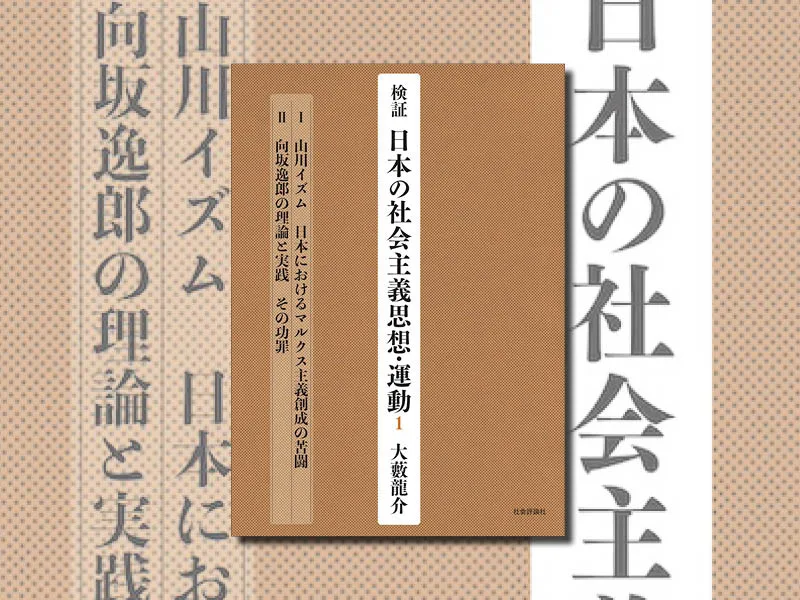
日本の社会主義がもつ百年有余の史的過程を分析し思想・運動上の根拠を探索する。
目次
Ⅰ
山川イズム 日本におけるマルクス主義創成の苦闘
1 社会運動の道
2 マルクス主義理論の体得
3 第一次共産党 結成と解散
4 無産政党の形成と山川の無産政党論
5 労農グループの形成
6 無産政党運動の発展と終末
7 プロレタリア革命の条件は実在しなかった
8 平和的な民主主義革命を求めて
(補)天皇制
9 山川新党への挑戦、蹉跌
10 晩年の理論活動
11 社会主義への道は一つではない
12 山川イズム論評の変遷
13 山川イズムの歴史的意義
Ⅱ
向坂逸郎の理論と実践 その功罪
1 戦前の活動
2 戦後初期の活動
3 『経済学方法論』―理論的原点
4 「資本主義的蓄積の一般的法則」―窮乏化論
5 社会主義革命論
6 社会主義社会論
7 三池闘争
8 向坂社会主義協会
俗学マルクス主義と社会党強化
9 社会党の停滞低落、社会主義協会の拡充強化
10 「日本における社会主義への道」と
「社会主義協会テーゼ」
11 ソ連讃歌
12 社会主義協会、隆盛から閉塞、分解へ
13 歴史的功罪
序(抜粋)
日本における社会主義思想・運動は、生成以来100年有余の歴史をもつが、今日ほど退潮し衰勢になったことはあるまい。戦後左翼勢力の主座を占めてきた社会党の消滅が表徴するように、日本の社会主義は危局に立たされている。
本書『検証 日本の社会主義思想・運動』は、その敗退の史的過程を分析し、思想・運動上の根拠を探索する。
19世紀末草創の日本社会主義は、大正デモクラシーを背景に、安部磯雄、片山潜、幸徳秋水、堺利彦、山川均らの先駆的事績を通じて礎石を築いた。
1917年のロシア革命、そしてソ連共産党・コミンテルンの世界共産主義思想・運動の興隆は、日本の社会主義思想・運動の展開にも深甚な影響を及ぼした。1922年の日本共産党の創立、その解散後の共産党の再建は、コミンテルンの強力な働きかけに依ったし、1926年からの第二次共産党はあらゆる面でコミンテルンに服した。それとともに、日本のマルクス主義勢力は共産党と労農グループに分立し、社会民主主義勢力の建設せる無産政党はそれを支持する労働組合・農民組合ともども、中間派、右派に分化した。
このマルクス主義と社会民主主義の諸政派間の軋轢と対抗関係は、戦後にも基本的に引き継がれ、およそ1970年代まで続いた。
1989~91年のソ連・東欧「社会主義」体制の倒壊により、ソ連共産党主導の20世紀社会主義思想・運動の破産は誰の目にも瞭然となった。親ソ連性を特質としてきた日本の社会主義には、決定的な打撃だった。
日本資本主義経済・社会・国家体制に対する社会主義的変革の闘いは敗退した。今求められているのは、失敗、敗北から徹底的に学ぶこと、そして多様な視角で新たなる再興への座標を定立することである。
著者略歴 著者紹介
大藪龍介(おおやぶ・りゅうすけ) 元福岡教育大学教授
1938年 福岡県三潴郡大木町生まれ
1961年 九州大学法学部卒業
1970年 九州大学大学院法学研究科単位取得退学
2024年12月6日刊
検証 日本の社会主義思想・運動1
大藪龍介 著
A5判352頁 2400円+税 ISBN978-4-7845-1221-8
購入サイト(外部リンク)