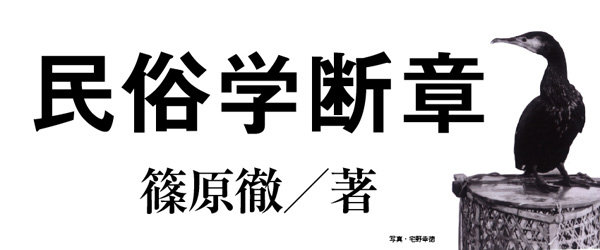滋賀県立琵琶湖博物館・篠原徹氏の著作『民俗の記憶 俳諧・俳句からみる近江(キオクノヒキダシ3)』より、冒頭の「はじめに」をお読みいただけます。第2回(全3回)
第2回
眼前のことどもを一行にこめて
篠原徹
(滋賀県立琵琶湖博物館)
しかし、考えてみれば近世の世界では、詩嚢の大きさと観察力の二つが文人としての必要不可欠な条件であったのは当然のことなのかもしれない。
近世の世界では圧倒的多数は農民であったが、彼らは「歩くこと」と「記憶すること」によって生活を成り立たせていた世界に生きていたからである。
眼前に展開する世界を自らの観察と言葉で記録をとるといえば民俗学や人類学のフィールドワークの作業である。書き記されたものがフィールドノートというものであるが、矢立で少々のことは記すことができても近世の旅ではそれほどふんだんに紙を使えるほど庶民は裕福ではなかった。
では眼前で展開した世界を自らの眼で観察し自らの言葉で書き記すことができないとなればどうするか。
それが俗信、自然暦、俳諧などに代表される「一行知識」というものである。
言わんとするところは俗信、自然暦、諺、俳諧の心性は同じ根本から出ている樹の枝葉ではないかということである(注:篠原徹「動植物をめぐる俗信とことわざと俳諧」『国立歴史民俗博物館研究報告第 一七四集』国立歴史民俗博物館、二〇一二年)。
詩嚢というのは俳人でなければ蘊蓄といってもいいものであるけれども、民俗学の創始者である柳田国男や小説家なら石川淳といった人たちが、和漢だけではなく泰西の学問や文学の膨大な素養をもった文人であった。
ここで話題としているのが俳諧・俳句なので、俳諧・俳句の詩嚢とはどのようなものなのか一例を挙げておきたい。
それは俳人・坪内稔典さんの著作が教えてくれた例なのであるが、漱石の「叩かれて昼の蚊を吐く木魚哉」の句に関するエピソードである。実はこの句近世の東柳という人の句に「たゝかれて蚊を吐く昼の木魚哉」があり、あまりに似ているので偶然ではないと想定されるというのである(注:坪内稔典著『俳人漱石』岩波新書、二〇〇三年)。
漱石がこの東柳の句を紹介している幸田露伴の随筆か太田南畝の『一話一言』を読んでいて、おそらく記憶の片隅に東柳の句が潜んでいたのであろう。
昨今、学問や文学の領域で偽造や盗用・剽窃が問題になるが、漱石の句が独創なのか盗用なのかということをここで問題にしているのではない。幕末から明治に生きた知識人・漱石という人の知のあり方こそが興味深い問題であり、近世の俳人たちの詩嚢のあり方も同じようなものであったと思うのである。
つまり近世の俳人たちの知のあり方は「歩く世界」と「記憶する世界」によって支えられていたが、漱石はその系譜を引く文人であったのではないか。
漱石がこの句を作った時東柳の句は忘却されていて記憶の片隅に押しやられていたにちがいない。しかし膨大な他者の句を詩嚢に収めていたので無意識に東柳の句が「キオクのヒキダシ」から取り出され創造の糸がこんがらがってしまったのであろう。
→第3回

通販サイト(外部リンク)
著者紹介 篠原徹(しのはら とおる)1945年中国長春市生まれ。民俗学者。京都大学理学部植物学科、同大学文学部史学科卒業。専攻は民俗学、生態人類学。国立歴史民俗博物館教授を経て、滋賀県立琵琶湖博物館館長を勤める。従来の民俗学にはなかった漁や農に生きる人々の「技能」や自然に対する知識の総体である「自然知」に目を向ける(「人と自然の関係をめぐる民俗学的研究」)。著書に『自然と民俗 ─心意のなかの動植物』(日本エディタースクール出版部、1990年)『海と山の民俗自然誌』(吉川弘文館、1995年)『アフリカでケチを考えた ─エチオピア・コンソの人びとと暮らし』(筑摩書房、1998年)『自然とつきあう』(小峰書店、2002年)『自然を生きる技術 ─暮らしの民俗自然誌』(吉川弘文館、2005年)『自然を詠む ─俳句と民俗自然誌』(飯塚書店、2010年)『酒薫旅情』(社会評論社、2014年)など。